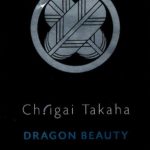特にブルゴーニュワインの話をしていると、除梗率の話はたびたび出てくるテーマのうちのひとつです。
この「除梗」の読み方は、梗を除くということで「じょこう」と読みます。
今回はこの除梗について、お話します。
除梗とは
除梗とはブドウについている茎や梗(下記写真の緑色の部分)という部分を外す作業のことです。

白ワインは皮や種、梗を取り除いて発酵させますが、赤ワインの場合は皮などを漬け込みながら発酵させますので、梗を除くか入れるか選択しなければなりません。
どのくらいの割合の梗を除くのかというのを除梗率と言い、生産者は自分の造りたいワインを目指して除梗率を決めています。
除梗の歴史的流れ
クラシックな造りと言いますか、ワインを造り始めた当時は除梗せずに全房発酵でした。
元々は技法に頼らずシンプルな造りが多く、除梗機もなかったので当然全房発酵です。

ワインを造る過程で葉っぱが入っていることさえあったようです。
除梗機が誕生した後も、その性能はまだまだ低かったようです。
除梗する過程で果実を潰してしまったり、果実に傷をつけてしまうことがありました。
そのため主流はまだまだ全房発酵でした。

除梗機を使わなければ果実に傷をつけるリスクを負わないで済みますので、除梗しないことを選択するのもわかりますね。
ようやく除梗機の性能が向上し始めたのは、1950年頃からでした。
性能が向上したことにより、除梗を取り入れる造り手も増えてきました。
除梗を取り入れた生産者と言えば、ブルゴーニュの神様、アンリ ジャイエ氏です。
アンリ ジャイエとは
アンリ ジャイエ氏は、ブルゴーニュの神様と呼ばれる造り手です。
アンリ ジャイエ氏は完全除梗でワインを作ります。
しかしここで疑問が出るのではないでしょうか。
「除梗をするとワインにどのような影響があるのだろうか?」
生産者はどのような効果を期待して、除梗率を考えているのでしょうか。
ここからは全房発酵と完全除梗について、その利点をそれぞれ挙げていきます。
完全除梗の利点
・味わいがクリアに仕上がり、ピュアで果実味が尊重されたスタイルになる。
・未熟な梗の青い香りが付きづらい。
全房発酵の利点
未熟な梗が入ると、青い香りがつくことがありましたが、近年温暖化の影響で梗がしっかりと熟すようになってきている。
・梗由来のタンニンが加わり、ワインに骨格を与えることができる。
・梗が入ることにより、醸造時の温度上昇が穏やかに進むため、複雑性を得ることができる。
全房発酵の懸念
クラシックな造りである全房発酵ですが、懸念材料もあります。
・梗が色素を吸収して、ワインの色を薄くする。
・梗からの水分により、アルコール度数が下がる
・梗が持つカリウムによって酸度が下がり、phが高まり、微生物が増殖する可能性がある→SO2を多く使用する必要がある。
↓
ブレタノミセスによる汚染リスク!!!
ブレタノミセスについて詳しくはこちらを参考にしてください。
様々な考え方
梗については両方の立場から、異なる考えがありますので、その一部をご紹介します。
テロワールを反映するために梗が必要
⇅
梗の要素がテロワールを隠す
丁寧な除梗が可能になったので、ピュアな果汁で発酵させることができる
⇅
温暖化によりふくよかなテイストの果汁が取れるようになったので、梗を入れて複雑味を出したい
このように考えの違いがありますので、どちらを選択するかは生産者の考え方によります。
生産者によっては何割かを全房で仕込んでいる人もいます。
全房発酵を行う生産者
現在、全房発酵を行う生産者は、全体の10%程度だと言われています。
温暖化の影響で、ワインがふくよかな造りになり過ぎないように、全房発酵を取り入れ始めている生産者が増えてきています。
DRC
プリウレ ロック
デュジャック
ルロワ
シャトー ド ラ トゥール
アンジェッロ ガヤ(イタリア)etc...
全房発酵を取り入れているのはなかなかビッグネーム揃いですね。
最後に
この記事では除梗について解説させていただきました。
生産者は様々な考え方の中で『全房発酵を行うか』『除梗するか』を考えているのですね。
ヴィンテージやキュヴェによって、除梗率を変える造り手もいます。
どちらが優れている、というわけではありませんが、眠気がきてしまうテクニカルシートもこのようなことを知っていると、少し楽しく読むことができますね。