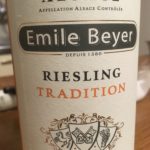一言でお酒と言えど、お酒には様々な種類があります。
ビールやワイン、ウイスキー、日本酒、焼酎……
これらは原料や製法、アルコール度数の高さなども様々です。
一体何がどう違うのでしょうか?
この記事ではお酒の種類についてお話させていただきます。
お酒の種類とは?醸造酒や蒸留酒、混成酒について解説
お酒は、醸造酒(じょうぞうしゅ)、蒸留酒(じょうりゅうしゅ)、混成酒(こんせいしゅ)の3つに区分することができます。
どのお酒も基本的にはこの3つのどれかに入ります。

この3つに入らないお酒ってあるのかな?という感じです
そしてこの『醸造酒』『蒸留酒』『混成酒』の違いは製法の違いです。
ではこれらの製法の違いを、できるだけわかりやすく解説していきます。
醸造酒
代表例:ビール、ワイン、日本酒など
まず基本的に醸造酒はすべてのお酒の基本ということができます。
基本的にお酒を造るためには、『酵母』という微生物の力を借りなくてはなりません。
酵母は自然界にも自然酵母(野生酵母)として存在していますし、培養酵母として造られているものもあります。

ワインの場合、ブドウの果皮に酵母が付着しています。
そのため自然にブドウが落下して果実が潰れた場合、果汁に酵母が入り込み、自然に発酵が起こります。

最初にできたワインは、ブドウが落下して潰れた結果自然にできあがったものだったと言われています。
『酵母』はアルコール発酵として、糖分をエタノール(アルコールの一種)と二酸化炭素に分解します。
このアルコール発酵を利用して作られたものが『醸造酒』です。
他のお酒に比べると、そこまで手を加えずに造られているので、「原料の個性がしっかりと反映された酒類」と言うことができます。
麦原料=ビール
米原料=日本酒
糖化について
先ほど酵母は糖分を利用してアルコール発酵を行っているとお伝えしました。
ここで問題なのですが、酵母は糖分という形でないと分解することができません。
そのため大麦などの穀物がもつデンプンはそのままでは酵母が利用することができないので、酵母が使用できる形に変える必要があります。
その作業を『糖化』と呼びます。
わかりやすく説明すると、麦芽を発芽させて温水に漬け込む(糖化)と甘~い麦汁ができあがりますので、ビールはその麦汁を利用して発酵させます。
蒸留酒
代表例:焼酎、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ、ブランデー、ウイスキーなど
『蒸留酒』はその醸造酒を蒸留したお酒です。
蒸留は小学校の頃に理科の実験で行ったものです。分かるかたもいらっしゃると思います。

私はお酒の勉強をするまで忘れていましたよ……
蒸留とはそれぞれ液体がもつ沸点の違いを利用し、蒸気を冷やして沸点の低い液体を取り出す作業です。
液体は加熱すると沸騰し水蒸気になるわけですが、その水蒸気を冷やしまた液体に戻します。
色々なものが混ざった液体だと、沸点の低いものから水蒸気になるので、戻した液体は沸点の低いもの中心に構成されています。
エタノール(エチルアルコール)は水よりも沸点が低いので、醸造酒を蒸留することによりアルコール度数の高い液体に変わります。
水の沸点は100℃、エタノールは約78.3℃
一般的に一回の蒸留(単式蒸留器を使用した場合)で約三倍のアルコール度数になると言われています。
茶色いお酒
ジンやウォッカは透明なのに、なんでウイスキーは茶色いの?
このような質問を今までに何度も受けたことがあります。
ウイスキーが茶色いのは樽で熟成させているからです。
樽で熟成していなくても、カラメルを添加して茶色いお酒もありますが、基本的に樽熟成が原因だと思っていいでしょう。
蒸留したてのお酒はすべて透明です。
蒸留したてで透明なお酒はニューポットと呼ばれています。
蒸留酒は原料の違いでその味わいは大きく異なるのですが、樽で熟成したかどうか、どのような樽で熟成させたか、によっても見た目や味わいに大きな影響を与えます。
この詳しいお話はまた別の機会で。
ウイスキーに関する情報はこちらのメディアがお勧めです↓
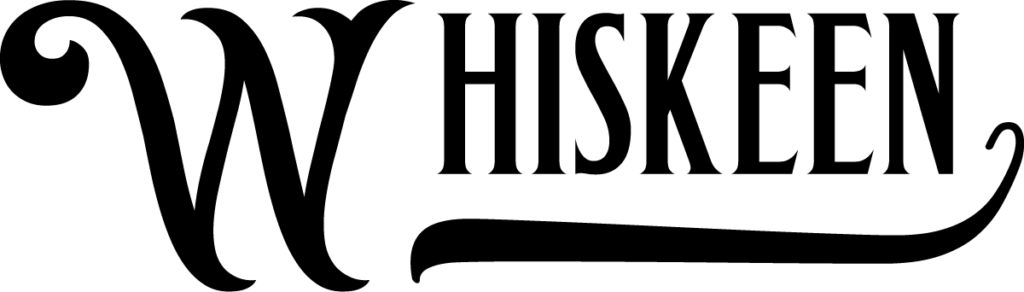
Whiskeen(ウイスキーン)はウイスキー好きが運営するWebメディアです。各ウイスキーの紹介や蒸留所スタッフのインタビュー記事など、ウイスキー好きに嬉しい情報が満載です。
混成酒
代表例:リキュール、ヴェルモットなど
『混成酒』は、醸造酒や蒸留酒にフルーツやハーブなどを浸けたり、添加したりして造られたお酒です。
お酒のベースとなる原料の風味というよりも、添加したもののフレーバーが強く感じられます。
僕ら日本人になじみある梅酒も混成酒の一種として扱われます。
最後に
今回はお酒の種類についてご説明させていただきました。
基本的にお酒は『醸造酒』『蒸留酒』『混成酒』に分けられるのでしたね。
日本酒やワインは好きじゃないけれど、ウイスキーやブランデー、焼酎は大好きという酒豪の方は、蒸留酒と相性が良いのかもしれませんね。
個々のお酒のご説明などはまた別の機会にお話させていただきます。