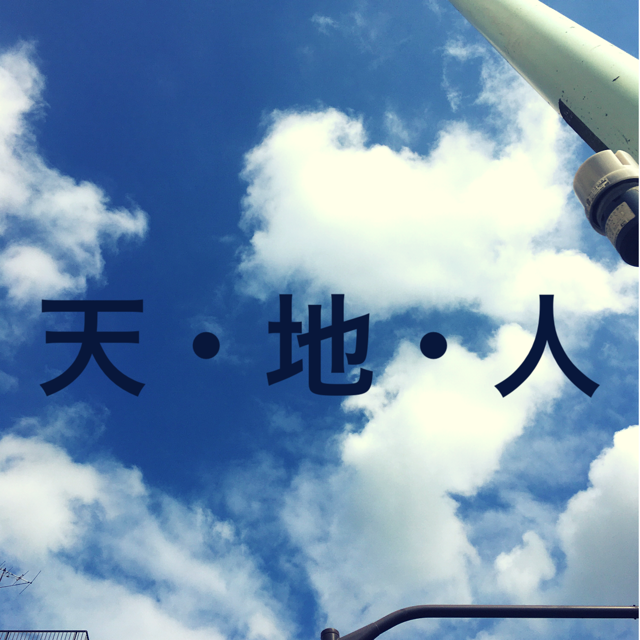皆様はどのようなきっかけでワインを好きになりましたか?
私がワインを好きになったきっかけは、赤ワインの味の違いがわかった時です。
赤ワインは渋くて飲みづらいもの、というイメージがあったのですが、そのときブルゴーニュのピノ ノワールを飲んで、このような赤ワインもあるのか!と感動した覚えがあります。
赤ワイン、白ワインともに味の違いや好みのタイプがわかると面白さが出てきます。
今回はそんなワインの味わいを決める要素の『天・地・人』について、簡単にお話しします。
ワインの味わいを決める要素とは?天地人の意味とは?
ワインの味わいは、『果実味』『酸味』『渋み(タンニン)』を捉えるとわかりやすいです。
その他には、アタック(口当たり)の強さや粘性、飲み口と余韻の間の味わいが太いか空洞か(わかりづらいですね)、余韻の長さなどが挙げられます。
そういった味わいは一体何によって決定されているのでしょうか?
これは残念ながら一言で言えるものではありません。
それはひとつの理由ではなく、いろいろな事象が関係してバランスをとり、味わいを形成しています。
そこで『天・地・人』という言葉があります。
この言葉は「ワインは天地人によって形成されている」というように使用されます。
この『天・地・人』とはそれぞれ何を表しているのでしょうか
それでは、ひとつずつ解説していきます。
天
その文字の通り、天とは天候を表す名であり、ヴィンテージごとの特徴や気候を表します。
ワインは農作物であるぶどうの出来に影響を受けるので、その年の天候と深く関係しています。
ぶどうの収穫前に雨が降りすぎると、ぶどうが水っぽくなってしまい、凝縮感にかける。
地
これも字の通り地とは土地の事であり、ブドウの育つ場所を指します。
冷涼な気候で造られたぶどうと、温暖な気候で造られたぶどうは味が違います。
冷涼な方が酸味が際立ち、シャープな印象やエレガントなワインが多いです。
温暖な気候だと、ぶどうがよく熟すので、ボリューム感や果実味が出ているワインが多いです。
フランスの特にブルゴーニュ地方で言われる概念で、『テロワール』というものがあります。
テロワール(微気候)とは、畑など小区画の違いによる個性の違いのことを言います。
水はけや畑の傾き、風の入り方など、まさに地の要素です。
この畑はすぐ下の畑よりも、少し高地にあり傾きもある。
なので下の畑のものよりも昼夜の寒暖差が付き、綺麗な酸味があり、エレガントな印象がつよい。
人
人とはまさに、ワインとは人の造るものという意味です。
ワインを造る際、人が手を加えることを指します。
逆に、今流行りのヴァン ナチュールはいかに人の手を排除できるか、を考えて造られたワインです。
ワインには様々な製法があり、その造り手がどのような方針でワインを造るかによって、味わいは変わります。
例えば除梗するかしないかも生産者の考え方次第です。
除梗について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
ピュアなワインを造りたいので、樽ではなくステンレスタンクで熟成させる。
あまり良いヴィンテージではなかったので、不良なぶどうを手作業で選別する。
最後に
天地人とは別ですが、やはりぶどう品種の違いは、ワインに大きな影響を与えていると思います。
梨の幸水などのように、ぶどうにも種類があります。
品種の話は長くなるので、また別の機会にお話しします。